ども。
節約投資家のぱんだマンです。
2022年4月1日より、SBI証券では人気のQQQやSPYDなどの米国ETFが買付手数料無料になります。
これによりETFによっては投資信託で保有するより圧倒的にコストが抑えられるので、保有コストを少しでも抑えたいと考えている人にとってはかなりの朗報です。
また今回SBI証券が買付手数料無料化したETFは、ポートフォリオに混ぜると面白そうなETFばかりですので一部取り入れてみてもいいかもしれません。
この変更を知って色々思うところがありますので、今回はそんなところを紹介させてください。
それではお願いします。
以前との比較
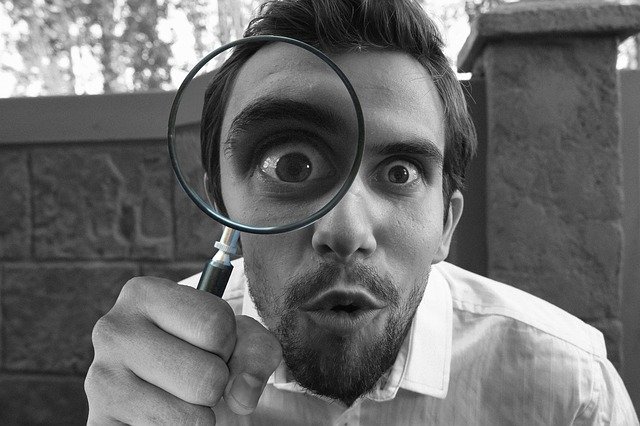
まず、買付手数料無料のETFは以前からありました。
それが今回、買付手数料無料の米国ETFを入れ替えて「SBI ETFセレクション」として生まれ変わります。
従来(2022年3月31日)の手数料無料の米国ETFは以下の9銘柄。
| ティッカー | 銘柄名 | 経費率 |
|---|---|---|
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.07% |
| VOO | バンガード・S&P500ETF | 0.03% |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% |
| SPY | SPDR S&P500ETF | 0.09% |
| IVV | iシェアーズS&P500ETFトラスト | 0.03% |
| EPI | ウィズダムツリーインド株収益ファンド | 0.84% |
| DHS | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド | 0.38% |
| DLN | ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド | 0.28% |
| DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長 | 0.28% |
正直、王道なインデックスファンドとそこまで有名でないETFの集まりって感じでした。
王道なインデックスファンドなら投資信託でもかなり低コストで優秀ですし、クレカ積立できる点や為替手数料が不要な点、分配金への課税等を考えればむしろ投資信託の方が優秀です。
その他のファンドについても同じもしくは似た指数に連動する上位互換で人気のETFがありますから、そちらの方がいいと思います(例、DHS→VYM、DGRW→VIG)
人気ファンドが一概にいいとは言えませんが、情報の集まりやすさや人気に裏打ちされた理由がありますので、自分で考えられる人以外は投資目的に合う人気ファンドがいいと思います。
以上がこれまであった買付手数料無料のETFですが、これが以下のように生まれ変わります。
| ティッカー | 銘柄名 | 経費率 |
|---|---|---|
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.07% |
| VOO | バンガード・S&P500ETF | 0.03% |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% |
| EPI | ウィズダムツリーインド株収益ファンド | 0.84% |
| GLDM | SPDRゴールド・ミニシェアーズトラスト | 0.10% |
| QQQ | インベスコQQQトラスト・シリーズ1 | 0.20% |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 0.07% |
| AGG | iシェアーズコア米国総合債券市場ETF | 0.04% |
| VGT | バンガード米国情報技術セクターETF | 0.10% |
| IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 0.41% |
銘柄数は1増えて10銘柄になり、中身もインデックスファンドと王道のセクターETFになりました。
かなりバランス良くないですか?
王道のインデックスファンドに成長性が高いグロース株ETF、安全性が高い債券とゴールドETFにキャッシュフローを良くする高配当株ETF、これだけでバランスの良い教科書的なポートフォリオができそうです。
投資信託+米国ETFで攻守揃う

先ほども言ったように王道のインデックスファンド(VT、VOO、VTI)は、投資信託の信託報酬も低く米国ETFでわざわざ持つ旨味は少ないです。
ですが、残りのETFに関しては似たような投資信託の信託報酬が比較的高い(もしくは連動する商品がない)こともあって、組み合わせによってはかなり理想的なポートフォリオを作成することができます。
例えば、
- 投資信託で「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を保有しつつ、期待リターンを上げるために「QQQ」や「VGT」を保有する。
- 出口戦略を考えなきゃいけない年齢になったから、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を積み立てつつ、値動きが小さい「GLDM」や「AGG」を混ぜてポートフォリオ全体での変動リスクを下げる
など、人気の投資信託と組み合わせて使うことでかなり投資の幅が広がります。
以前、S&P500を少しでもアウトパフォームするETFの組み合わせを検証していますのでご参考ください。
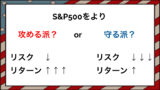
もちろん米国ETFに投資する以上為替リスクを伴いますが、それは投資信託でも同じこと。
人気のインデックスファンドは為替ヘッジがついてないものばかりなので、円高にふれてしまえば評価額は下がります。
しかしインデックス投資をしている方の出口戦略は4%ルールが基本なので、使い切るまでには相当な時間があるはずです。
それを考えれば為替リスクも長期で分散されるのであまり気にしないで良いと思いますよ。
楽天証券とマネックス証券もあるが、オススメしない

ちなみにですが、SBI証券のライバルである楽天証券とマネックス証券でも買付手数料無料の米国ETFはあります。
それぞれ対象銘柄を見てみましょう。
楽天証券
| ティッカー | 銘柄名 | 経費率 |
|---|---|---|
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.07% |
| VOO | バンガード・S&P500ETF | 0.03% |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% |
| SPY | SPDR S&P500ETF | 0.09% |
| RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 0.25% |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 0.10% |
| AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 0.68% |
| FINX | グローバルX フィンテックETF | 0.68% |
| GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF | 0.50% |
王道インデックスとセクターETF、テーマ型のETFとバランスは取れてるものの微妙なラインナップです。
特にグローバルXのテーマ型ファンドは長期積立するものではないので、個人的にはないですかね。
補足:3月30日、楽天証券が買付手数料無料銘柄を拡充したことを発表。
これにより2022年3月31日(木)現地約定分より、SBI証券とほぼ同じETFを無料で買えるようになりました。
マネックス証券
| ティッカー | 銘柄名 | 経費率 |
|---|---|---|
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.07% |
| VOO | バンガード・S&P500ETF | 0.03% |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% |
| SPY | SPDR S&P500ETF | 0.09% |
| IVV | iシェアーズS&P500ETFトラスト | 0.03% |
| EPI | ウィズダムツリーインド株収益ファンド | 0.84% |
| DHS | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド | 0.38% |
| DLN | ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド | 0.28% |
| DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長 | 0.28% |
こちらは変更前のSBI証券と全て同じ銘柄です。
なので同じ理由でオススメはできません。
そもそも米国ETFに投資するならSBI証券一択
個人的に思っていることですが、米国ETFを含む海外ETFを購入するならSBI証券が最も良いです。
海外のETF(もしくは個別銘柄)を購入する場合、コストとなるのが売買手数料・為替手数料・経費率ですが、このうち買付手数料に関しては無料になりますし、経費率はどの証券会社で購入しても同じです。
ただ為替手数料に関してはSBI証券の圧勝です。
住信SBIネット銀行の外貨積立を使って入金すれば、為替手数料は他証券の1/10以下に抑えることができます。
加えて、コーポレートアクションのこともあります(楽天証券の場合)
追記:2022年5月30日(月)以降、米国株式のコーポレートアクションについての処理が改善され、SBI証券・マネックス証券とほぼ同等なレベルにまで特定口座内で対応してくれます。
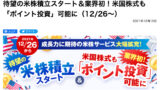
なのでIPO狙いでマネックス証券を利用する以外は、SBI証券で十分だと思いますよ。
面白そうだが、まだ様子見

個人的には似たような投資信託がない「VGT」と「EPI」、投資信託の実質コストと経費率の差が大きい「QQQ」にかなりそそられるものの、もう少し様子見したいと思います。
理由はやっぱり”いつまで無料なのか不明”ってこと。
長期投資を考える上では、「いつまで手数料無料で購入できるのか」ってのはトータルコストに関わる最重要項目です。
今回もそうでしたが、手数料無料銘柄は入れ替え制なのでSBI証券の差配一つで大きく変わります。
それを考えると、似た投資信託がない「VGT」と「EPI」は有料化しても積み立て続けられるのか不安ですし、似た投資信託(iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス)に投資している以上、『QQQに変えなきゃよかった』と思いそうです。
まぁ、クレカ積立や投信マイレージが改悪される可能性と手数料無料銘柄から外される可能性、どっちが高いかって話なんですが。
それに多少のコスト差なら、投資信託の方が購入するのも保有するのも楽です。
私は中国のハイテク株がひとまとめになっている米国籍ETF「CXSE」を毎月積立投資しているから分かるのですが、ドル転の手間や入金の手間はかなり面倒です。
一応、住信SBIネット銀行の米ドル自動積立設定やSBI証券での自動積立設定はやっているものの、外貨の入金は自動化できないし、ETFの特性として投資額に余りがでます。
加えて分配金の再投資も自分でやらなきゃ複利効果が薄れますし、外国税額控除も面倒です。
それを考えれば、たかが信託報酬0.1%程度の誤差を甘んじて受け入れた方が結果的にお金は増えると思います。
なので個人的には様子見。
ですが、投資の選択肢が増えること自体は喜ばしいことですし、年齢や個々のリスク許容度によって細かくポートフォリオを調整できるのはいいことです。
王道なインデックスファンド一本に『少し物足りない』と感じている人は、是非試してみてはいかがでしょうか。
今回は以上です!
have a pandaful day



コメント
米国株の王道であるVOO,VTI
米国以外にも分散投資したい人はEPI,VT
逆に近年高成長の米国ITに集中投資するならQQQ,VGT
配当収入を重視する人の為のSPYD
株式以外のアセットに投資できるAGG,GLDM,IYR
これはもう、非の打ち所がない10選ですね(笑)
ところで少し思ったのですが、米国株投資信託(円建て)+GLDM(ドル建て)という組み合わせは効果的なのでしょうか?
教科書通りならば、アメリカの株価が下落している時は金価格は上昇しているものの、ドル安になっているので日本円にすると少し損です。
為替の影響を抑えるならば
米国株投資信託(為替ヘッジなし)+金投資信託(為替ヘッジあり)
米国株ETF+GLDM
というように円建てかドル建てで統一する組み合わせの方がいいと個人的には思うのですが、ぱんだマン様はどうお考えですか?
まず米国株投資信託に関してですが、円で積立していようが裏では米ドルに変えて投資しているので為替の影響は受けます(評価額が変動します)
ですが長期で見ればドル円は80〜120円の間を行き来しているし、長期投資なら為替変動も平準化される+株価の上昇幅の方が大きいので、高いコストを払ってまで為替ヘッジありの米国株投資信託を買う必要はないと思います。
米国株ETFと米国株投資信託はどちらが買いやすい・続けやすいかで選べばオーケー。
どうせ売却しなければ為替がいくら振れても、評価額が変わるだけで損も得もないですから(この変動を抑えたいなら為替ヘッジはあり)
金に関してですが、まずは大前提でポートフォリオに混ぜるのは50代以降の資産を守る段階に入ってからです。
資産を積極的に増やす段階で、利息を生まない金は不要なアセットだと考えます。
50代以降の出口戦略を考えるなら、GLDMのような米国ETF(ドル建て)より為替ヘッジありの金投資信託(円建て)の方がいいと思います。
その理由は、資産を取り崩す段階に入って株式が暴落した場合に、株式が回復するまで高騰する金から取り崩したいからです。
その時に円高(有事の円買いという言葉もありますが、有事のドルという言葉もある)に振れてしまえば、金の評価額も大きく減ってしまいます。
金も円建て・ドル建て関係なく、世界の市場では1TOZあたり〇〇ドルで取引されています(円建ての場合は、この価格を〇〇円に直す)
なので円建てでも結局為替の影響は受けるので、その分は為替ヘッジをかけてでも為替リスクを運用会社に負ってもらった方がいいと思います。
なので私の結論としては、
株式に関しては円建てドル建てどちらも良いが、為替ヘッジは両方不要。
金に関しては円建ての投資信託で為替ヘッジあり一択。